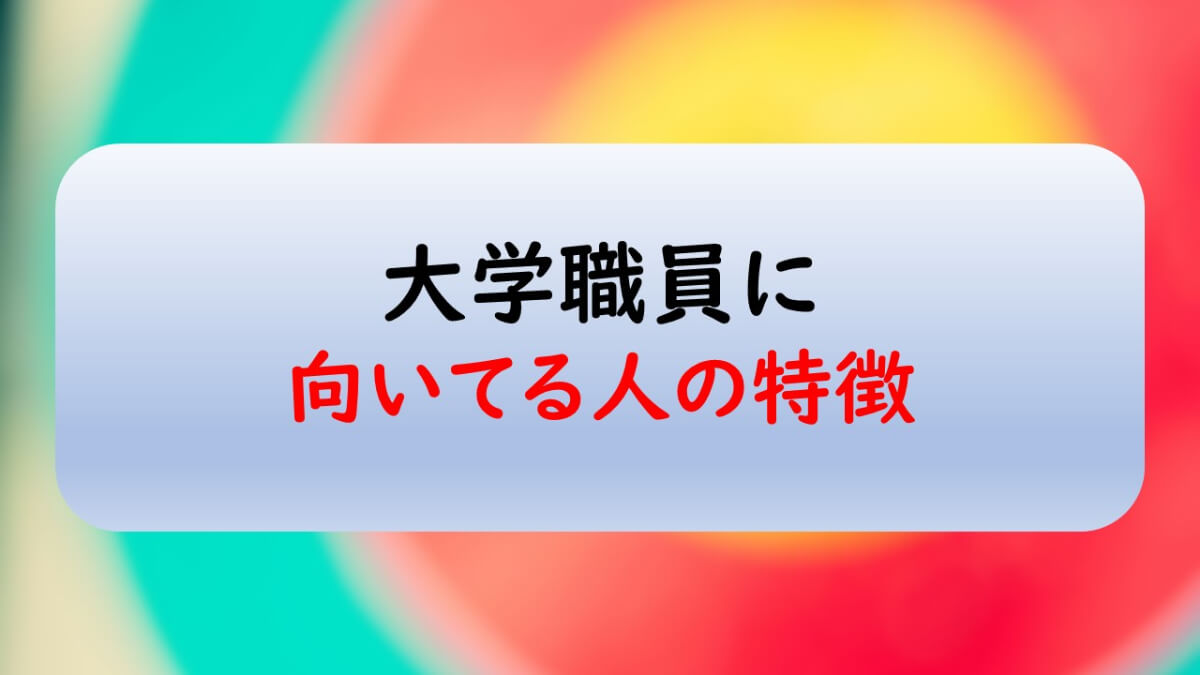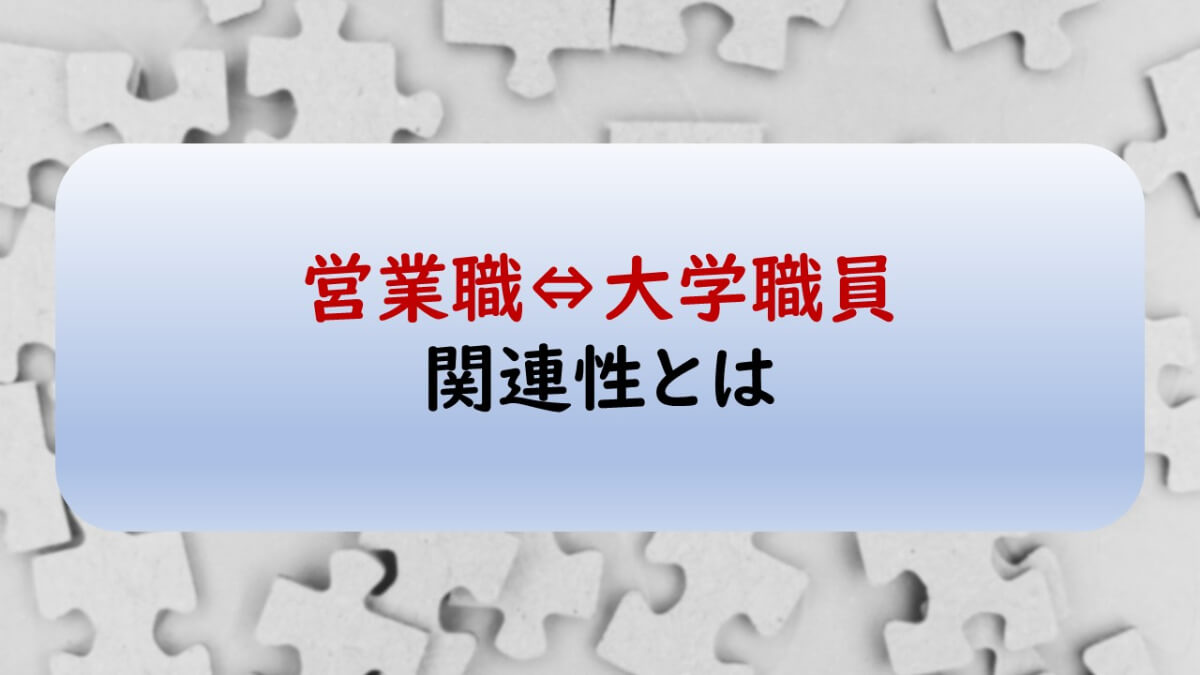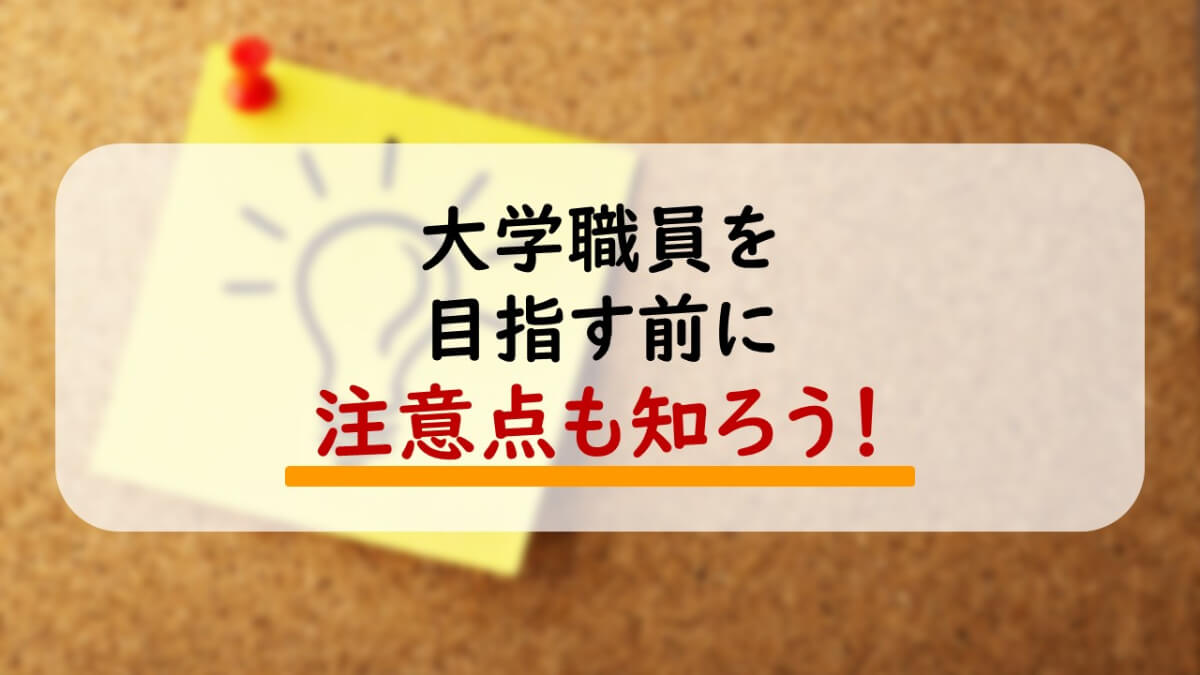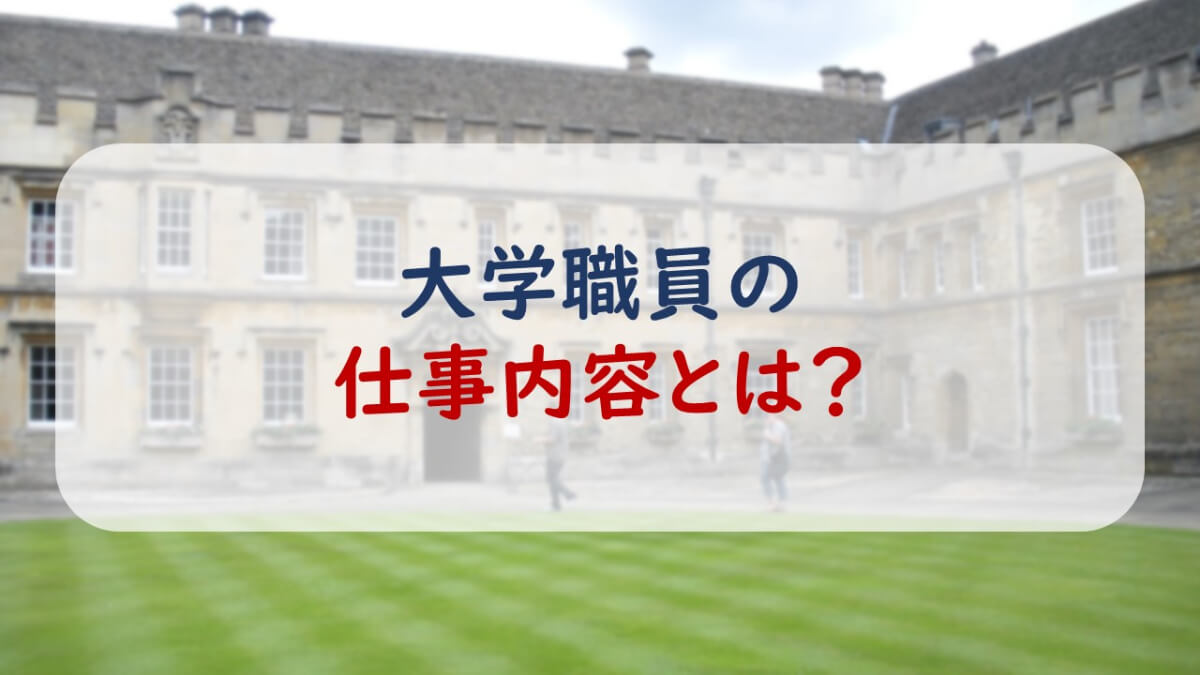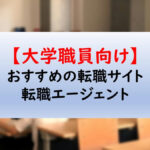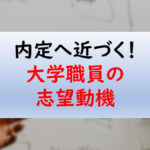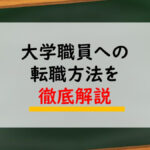どこの職種・職場においても、活躍している人は必ずいると思います。
マネジメント能力が高い人、毎年優秀な営業成績を残している人、同僚や取引先からの信頼が厚い人など・・・
所属している会社・部署によって、活躍しているという評価は違ってくると思いますが、「大学職員」において活躍している人とはどのような人でしょうか。
どのような人が大学職員として活躍していけるのか・向いてるのか、逆にどのような人は大学職員に向いてないのかを本記事では紹介していきます!
大学職員に向いてる人の特徴4選

まずは私なりに考えた大学職員に向いてる人、活躍できそうな人の特徴を紹介します。
細かく分けていくともっと多くの特徴が挙げられると思いますが、特に強く感じたものを4つピックアップしました。
- 積極的にコミュニケーションが取れる人
- チームで働いていける人
- ルーティンワークが苦にならない人
- ホスピタリティ精神に溢れている人
積極的にコミュニケーションが取れる人
大学職員の働き方をイメージして、事務職ということもあり黙々とデスクに向かって仕事をしていると想像する方も多いと思います。
私も大学職員になる前はどちらかと言えばそうなのかな?と想像していましたが、想像していた以上に様々な立場の方とコミュニケーションを取る機会が多いです。
例えば、学生・教員・他部署の職員・取引先・保護者・近隣地域の住民・卒業生など・・・
ただその中には、窓口や電話での相談対応など、受け身のコミュニケーションでも問題なく成立するものもあります。
ですが、大学職員として活躍していくためには、積極的且つ自発的にコミュニケーションを取らなければいけないと私は考えます。
例えば、前年踏襲の仕事だけではなく新しい取り組みや仕事を行う機会も現在の大学職員には度々求められます。
そのような際には所属部署だけでなく、様々な他部署の職員や先生方と協力して進めていくことが多いですが、そこで積極的にコミュニケーションを取れるかどうかで過程や結果に大きく影響すると考えます。
気難しい先生に丁寧なアプローチをすることや上層部への根回しも時には必要になるかもしれません。
そのようなコミュニケーションを入職歴に関わらず臆せずに出来ている人は活躍できると考えます。
チームで働いていける人
大学職員の仕事の中には、個人で完結する仕事もたくさんありますが、チームで動かなければいけない仕事も多く存在します。
入試やオープンキャンパス、学内企業説明会、入学式・卒業式などの大きなイベントの実施から、毎月・毎週の定例会議など、業務を分担し1つの仕事を完遂させます。
そのため、前述したコミュニケーション能力にも繋がってきますが、自分1人が良ければ終了ではなく、チームで動いていく働き方も必要となります。
私はずっと営業職だったため、自分1人の成績や結果が良ければそれでOKという働き方をしていたので、入職した当初はチームでの働き方に少し戸惑うこともありました。
チームで働くことが得意な方、協調性がある方は大学職員として適性があると思います。
ルーティンワークが苦にならない人
厳しい少子化の時代において、大学の生き残りをかけて各大学が新しい取り組みや改革を近年積極的に行っています。
そこに職員も携わる機会はあり、普段とは違う新しい仕事を行うこともありますが、大学職員は事務仕事がベースとなるため、ルーティンワークも多くこなしていくこととなります。
多くの大学ではジョブローテーションの制度を取っていますが、同じ部署にずっと所属していれば、毎年同じ時期に毎月・毎週同じような仕事をしなければならないかもしれません。
そのため、常に新しい仕事をしたい方やルーティンワークを苦に感じる方などは、大学職員に向いていないかもしれません。
ホスピタリティ精神に溢れている人
この特徴は特に、学生や教員・受験生などと多く接していくことが中心の部署(学生課や教務課・入試課など)の職員に該当します。
窓口があり、相談・調整対応が日々の仕事の中心となっている部署の職員には、ホスピタリティ精神やサービス精神が求められます。
とは言っても、高級ホテルのように常に笑顔で愛想良く丁寧にという対応である必要はないと個人的に考えていて、それよりも、的確に相談の内容を受け止めて規則に則り然るべき対応をスピーディーに行うことが大学職員に必要なホスピタリティだと思います。(もちろん、最低限のマナーや振る舞いは必須です。)
また、相談対応についても、時には同じような相談が来てルーティンのように対応しないといけない場面もあるかと思いますが、そのような際もホスピタリティ精神を忘れずに対応することが必要ですね。
大学職員に向いてない?人の特徴

続いて、先ほどとは逆に、私が考える大学職員に向いてないかもしれない人の特徴を紹介します。
前述した向いてる人の特徴4選の裏返しになるものも一部含まれていますが、以下の2つをピックアップしました。
- 実力主義・成果主義で働きたい人
- 自身が前に出て働きたい人
実力主義・成果主義で働きたい人
大学職員の人事評価制度は基本的に年功序列の傾向が未だに色濃く残っています。
また、大学職員には営業職のように目標達成やインセンティブでの評価もないため、個人の結果を出して評価されたい人や職歴に関係なく実力でのし上がって行きたい人には合わないかもしれません。
自身が前に出て働きたい人
大学職員は事務職の仕事を中心に、学生や教員を支えていく・支援していく働き方が多くなります。
受験生や保護者、取引先相手に話やプレゼンをしたり、前に出る機会もありますが、部署や立場によって制限されるため、全員にそのような機会が与えられるわけではありません。
そのため、自分自身が主役となって常に前に出て働いていきたいと考えている人が大学職員になると、ギャップが生まれる可能性が高いです。
向き・不向きは働く環境にも左右される

大学職員に向いてる人と向いてない人の特徴を紹介しましたが、この特徴は私の経験に基づくものなので、働く大学によっては全く当てはまらない可能性もあります。
そのため、特に向いてない人の特徴として紹介したものに関しては、参考までに読んでもらえたら幸いです。
また、本記事を読んで「自分は大学職員には向いてないのでは?」と感じた方もいるかもしれませんが、向き・不向きは自分自身でその環境で働いてみないと分からないというのが真実だと思います。

大学職員として働きたい・活躍したい気持ちが強いのであれば、まずは大学職員に挑戦して飛び込んでみてからでも良いかなと思います。参考になれば嬉しいです。