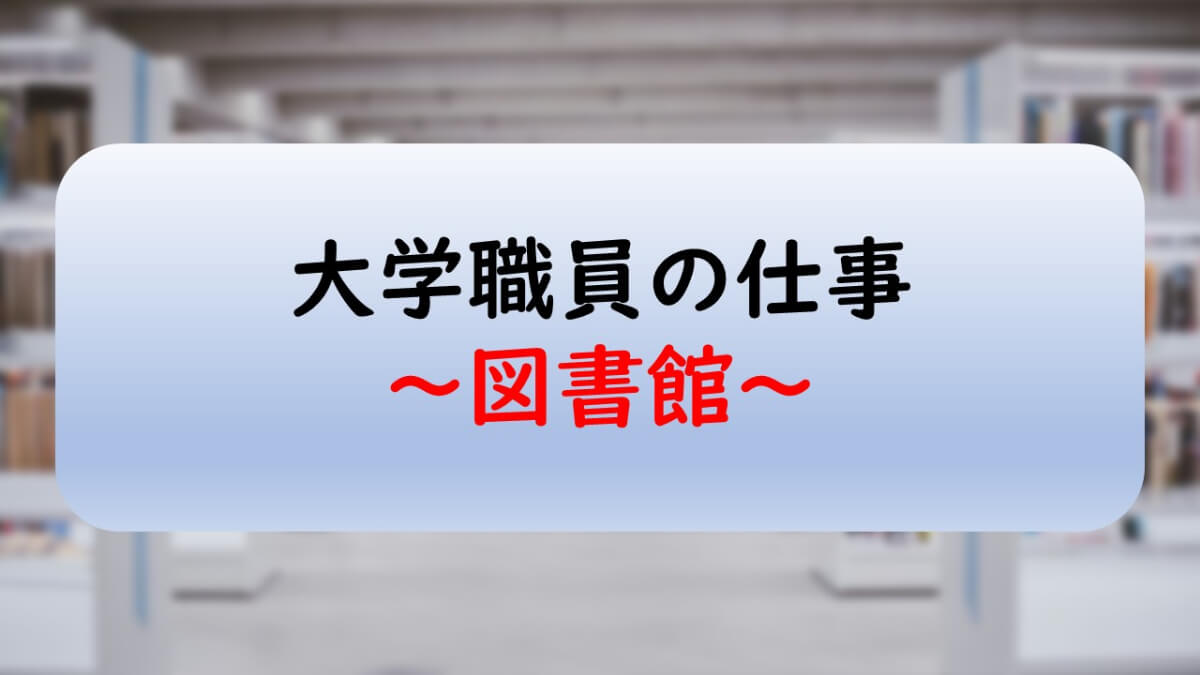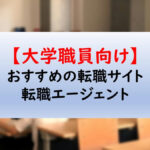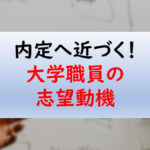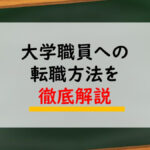大学職員の仕事紹介、図書館編です。
「図書館は専門的なスキルや資格を持った人しか働けないのでは?」
私も大学職員になるまではこのように考えていました。
ですが、大学職員になると新卒・中途採用かかわらず、図書館へ配属される可能性があります。
「本の貸し出しをするだけの部署?」と思われがちな図書館ですが、実際には教育・研究の基盤を支える専門的且つ大学の中でも重要な役割があります。
こちらの記事では、現役大学職員の立場から「大学図書館での仕事内容」・「やりがい」・「他部署との違い」を紹介します!
図書館での大学職員の主な業務内容

図書館配属となった職員は、その設備を存分に活用しながら学生や教員の学習・研究をサポートすることが最大の役割です。
図書館の仕事と聞くと1番想像しやすい本の貸出等の利用者サービスはもちろん、電子リソースの契約や学習・研究支援、展示企画など、幅広い業務があります。
「静かで落ち着いた職場」とイメージされがちですが、実際には裏方で慌ただしく動き回る日々も多く、教務系や管理系の仕事とはまた違った専門性とやりがいがあります。
利用者サービス(貸出・相談業務)
カウンターでの貸出・返却対応に加え、資料の探し方をサポートする「レファレンスサービス」も行います。
例えば・・・
- 「あるテーマについて本や論文を探したい。」
- 「特定の統計データや古い新聞記事を調べたい。」
- 「研究に必要な専門書の所在を知りたい。」
といった質問に対して、司書や職員が資料を紹介したり、検索方法を案内したり、必要に応じて他機関からの取り寄せをサポートするのがレファレンスサービスです。
日々の課題レポートでの参考文献探しや卒論で悩んでいる学生の相談に乗り、一緒に文献を探すこともあります。
学習・研究支援
大学図書館の大きな役割のひとつが「学習・研究支援」です。
単に本を貸し出す場所ではなく、学生や研究者がそれぞれの目的を達成できるように職員が多角的な支援を行います。
学習・研究支援は、図書館職員が「裏方」にとどまらず、利用者と直接向き合い、教育・研究活動を一緒に支える場面が多いのが特徴です。
具体的にどんなことを行っているのかいくつか例で紹介します。
情報リテラシー教育・授業との連携
新入生ガイダンスや授業内で、資料の検索方法、データベースの使い方、参考文献の書き方などを教えるプログラムを実施します。
また、教員と協力して「図書館を使った調べ学習」の授業を設計することもあります。
図書館職員が授業の一部を担当し、学生に資料探索スキルを身につけさせる取り組みは広がりを見せています。
近年はオンライン教材やオンデマンド動画を用いた学習サポートも一般的になっています。
学習環境の提供
自習室やグループ学習室の整備、パソコン・プリンタの利用環境、Wi-Fi完備など、学習しやすい場を整えることも重要な支援の一部です。
「きれいな図書館が入学の決め手となった。」・「高校とはまったく違う図書館の設備に惹かれた。」という在学生の声を度々聞いたことがあります。
図書館が人気の大学でイメージすると、立命館大学や東洋大学・国際基督教大学・国際教養大学などの図書館がパッと想像できます。
入学後に多くの時間を過ごすことになる図書館が受験生の入学の判断材料になることも珍しくないため、図書館の学習環境の充実した設備を整えることは大学全体としても非常に重要です。
地域や他大学との連携
他大学図書館との相互利用協定を通じて文献の貸し借りをしたり、地域住民向けに学習支援イベントを実施することもあります。
大学が持つ知的資源を社会に還元する重要な活動です。
私の所属している大学でも、近隣の地域の方に図書館を開放したり、地域の方々向けに様々な講座を積極的に開いたりしてます。
図書館運営・企画
展示やイベント開催の企画を行えるのも図書館の魅力です。
展示では、その時に旬の本をテーマを決めて並べたり、話題になっている本をコーナーにしたり、利用者に刺さる展示ができるよう工夫します。
イベント開催では、図書館単独で行うこともあれば、他部署と協力して図書館の施設をうまく活用して、学生向けのイベントを行うこともあります。
電子情報資源の管理【図書館業務の大きな変化点】
近年の大学図書館業務において、特に重要性を増しているのが 電子情報資源(Electronic Resources)の管理 です。
かつては紙媒体の書籍や雑誌が中心でしたが、今では学術データベース、電子ジャーナル、電子書籍、オープンアクセス資料など、オンラインで利用できるリソースが急速に拡大しています。
電子情報資源の管理は、一見すると裏方の業務に見えますが、大学の学術研究や教育活動に直結する非常に大切な仕事です。
契約・ライセンス管理
大学図書館は出版社やベンダーと契約を結び、学生や教員が学術データベースや電子ジャーナルを利用できるようにします。
この際には以下のような注意点があります。
- 同時アクセス数の制限(例:同時に10人までアクセス可能など)
- 学外アクセスの可否(VPNや認証システムを経由して利用可能にするか)
- 著作権・利用範囲(授業資料に利用可能か、印刷・ダウンロード制限はどうか)
契約内容を正しく理解し、大学内で適切に周知・運用するのも職員の大切な役割ですね。
システムとの連携
電子情報資源は図書館のOPAC(蔵書検索システム)やディスカバリーサービスに登録され、学生が検索できるように整備されます。
また、学認などの認証システムと連携させることで、学外からでもアクセスできるようにするケースが増えています。
こうしたシステム構築やベンダーとの調整も、裏方で職員が支える重要な仕事です。
利用統計・コスト管理
電子リソースは年間契約で数百万円単位になることも珍しくありません。
大学の予算は基本的に限られているため、その予算の中で、どのデータベースや電子ジャーナルを継続するかは重要な判断です。
そのために職員は以下のようなデータを収集・分析します。
- 利用回数(ダウンロード数やアクセス件数)
- 利用者層(学部生か大学院生か、特定学部での利用か)
- コストパフォーマンス(1回あたりの利用にかかるコスト)
こうした分析を踏まえ、事務局の上層部、教員や図書館委員会に報告・提案するのも図書館職員の役割です。
電子と紙のハイブリッド管理
電子リソースが中心になりつつあるとはいえ、紙媒体の図書や雑誌も依然として重要です。
図書館職員は 紙と電子の双方をどうバランス良く整備するか を考え、学生・研究者の学びを支える役割として活動しています。
図書館で働くには司書資格が必要?
図書館での専門職(正規職員)として働くには、原則として図書館司書資格が必須です。
ですが、大学職員として図書館で働く際には必須ではない大学が多いです。(私の大学も必須ではなく、司書資格を持っている職員は一握りです。)
ですが、「司書資格」を持っていると図書館で働く際には大きな強みになりますので、参考までに司書資格について少し紹介します。
司書資格の取得方法
司書資格は「図書館法」に基づく国家資格で、以下のルートで取得できます。
大学で司書課程を履修する方法
文学部や教育学部などに併設されている場合があり、所定の科目(図書館概論、情報サービス論、児童サービス論など)を修めれば卒業と同時に資格を取得可能。
通信教育で取得する方法
社会人でも取りやすいルート。放送大学や一部私立大学が通信課程を設けており、働きながら学習できる。
短期集中講習で取得する方法
大学を卒業していれば、文部科学大臣が指定する養成講習を受講して司書資格を取得することも可能。
司書資格が活きる場面
- 資料の選定・目録作成など専門性の高い業務
- レファレンスサービス(調査・検索支援)
- 図書館システムやデータベースの活用
司書資格を持っていなくても図書館勤務は可能ですが、知識があると業務理解が深まり、キャリアの幅も広がります。
他の部署でも同様のことがいえると思いますが、せっかく配属になったのであれば、その部署での専門的な知識やスキルを身に着けていくことは大学職員として大切な心構えですね。
大学職員として図書館を目指す方へのアドバイス

図書館は大学職員の中でも人気の高い部署のひとつです。
学生や研究者の学びを支えるという点で非常にやりがいのある仕事ですが、その分、採用後すぐに専門性が求められるケースも少なくありません。
これから大学職員を目指す方や、すでに職員で図書館配属を希望する方に向けて、いくつか私なりのアドバイスをまとめます。
司書資格の取得を検討する
図書館業務に必須ではありませんが、司書資格を持っていると選考や配属時に有利になることがあります。
資格がなくても図書館に配属されることはありますが、取得しておくと入職後の業務理解がスムーズです。
社会人であっても通信制大学などで取得が可能ですので、早めに準備しておくと安心です。
デジタル知識を積極的に身につける
図書館の仕事=本の貸し借り、というイメージはすでに過去のものです。
現在の大学図書館では、電子ジャーナルやデータベースの契約・運用、リポジトリの管理、検索システム(OPAC)の改善など、デジタル関連の業務が増えています。
基本的なITリテラシーはもちろん、データベース検索の知識、Webシステムに関する理解があると大きな強みになります。
コミュニケーション力を磨く
図書館は静かに仕事をしているイメージがありますが、実際は学生・教員とのやりとりが非常に多い部署です。
レファレンス対応、研究者からの購入依頼対応、ゼミ単位での資料利用サポートなど、人と接する場面は日常的です。
「人の学びを助ける」姿勢を大切に、相手の意図を汲み取るコミュニケーション力が求められます。
キャリアプランを意識する
図書館に長く配属される人もいれば、数年で学務や入試など他部署へ異動するケースも珍しくありません。
異動は個人の希望よりも大学の人事方針に左右されるため、図書館だけでキャリアを積み上げたいと考えるとギャップを感じることがあります。
「図書館経験をベースに、大学全体の運営にどう貢献できるか」という視点を持つと、異動後も前向きにキャリアを築けると考えます。
「研究・教育支援」という視点を忘れない
図書館業務の本質は「学術情報の提供を通じて、研究・教育を支援すること」です。
単なる資料管理にとどまらず、大学全体の教育・研究活動にどう寄与できるかを意識すると、仕事のやりがいも高まりますし、他部署からの信頼も得やすくなります。
まとめ
大学職員として図書館に配属されると、紙媒体とデジタル資源の両方を扱いながら、学生・研究者の学びを支える非常にやりがいのある仕事に携わることができます。
その一方で、専門的な知識やスキルが求められるため、事前の準備と心構えが重要です。
司書資格の取得やデジタル知識の習得、そして「人の学びを支える」というマインドを大切にすることで、図書館職員として活躍・成長できると考えます。
図書館と聞いて、静かな場所で静かに働くというイメージと実際の図書館での仕事は合っているところもあれば、まったく違う場面もあると思います。

図書館で働けるという経験は、まさに大学職員ならではの仕事で、私もいずれ携わってみたい部署の1つです。
皆さんの大学職員の仕事の理解を深める一助と参考になれば幸いです!