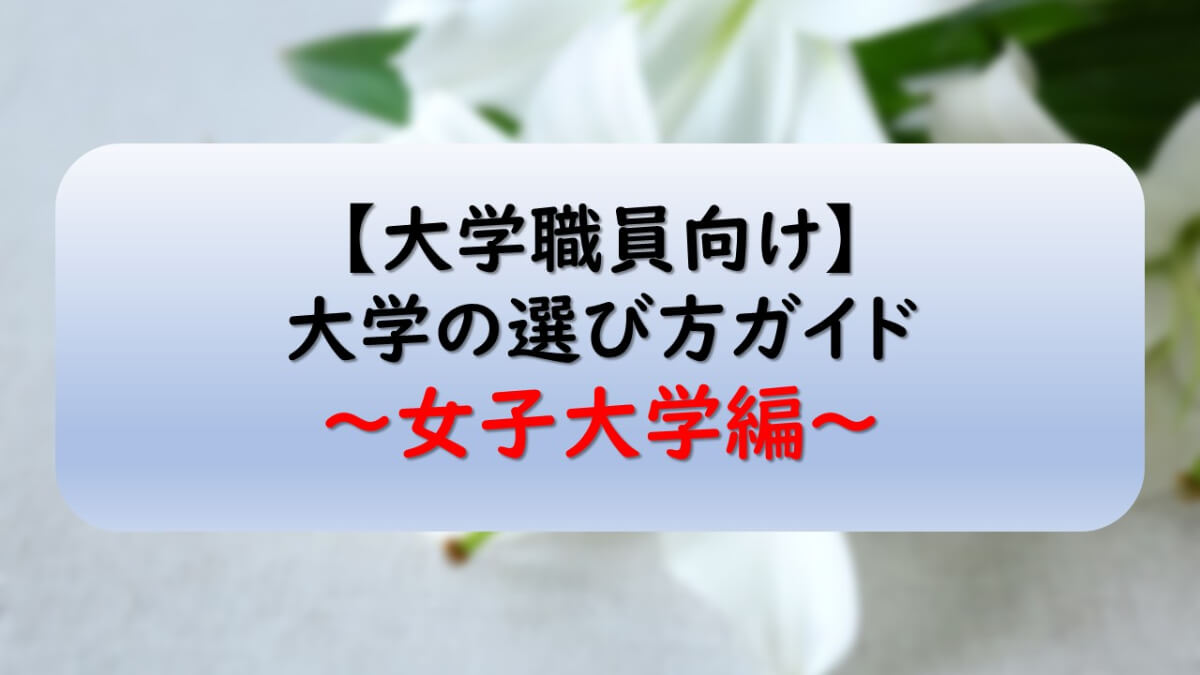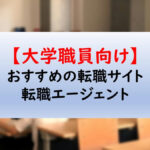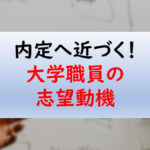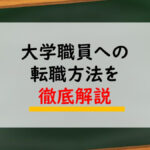皆さんも受験生だった頃に大学選びを経験されている方は多いと思います。
受験生だった頃は、偏差値の高さやブランド力の高さ・就職実績などで選ばれた方が多いと思いますが、大学職員として大学で働く際に、どのように大学を選べばいいのかはまた別の話となります。
現在、日本に約800もの大学がひしめき合う中、大学をグルーピングして、それぞれの特徴やおすすめポイント、職員として向いている方の特徴などを紹介します。
こちらの記事では、「女子大学」の職員をテーマに紹介していきます!
女子大学とは

女子大学はその名前のとおり、女性のみを受け入れている大学のことです。
女子大学は、明治・大正時代に誕生し現代までに、社会的な女性の役割やニーズに応じて変遷してきた背景があります。
はじめに、簡単に各時代における女子大学の歴史について紹介します。
明治末期〜昭和中期
当時は、女性の高等教育自体が希少だったため、「良妻賢母」を育成することが目的とされ、家政学を中心とした実用的な学びが重視されていました。
主な学部としては、以下のとおりです。
主な学部
- 家政学部(被服・食物・住居など生活技術、栄養学など)
- 文学部(英文学・国文学・哲学・史学など)
- 教育学部(児童学・保育・看護など)
明治末期頃は、「家庭」を前提とした学びが中心でしたが、「社会」での女性の就業や活躍を背景に徐々に学びも変化していきました。
また、家政学部や文学部の拡充に合わせて、短期大学の併設も進んでいきました。
高度経済成長期〜1990年代
自立した女性・働く女性の育成をミッションとし、女性の社会進出・グローバル化・少子高齢化社会などの時代背景への対応に基づき、以下のような学部が新設・改組されていきました。
主な学部の新設・改組
- 人間関係学部・人文学部・社会学部・国際学部・現代教養学部などの新設
- 家政学部 → 生活科学部・人間生活学部 への改称
- 看護学部や保健医療系学部の新設
2000年代〜現在
女性のキャリアの多様性・社会から女性に対して求められるニーズに対応するため、以下のような現代的な学部の新設、変化が活発に現在も行われています。
主な学部の新設・改組
- データサイエンス学部・ビジネス学部などの社会に直結する実学的な学部
- ダイバーシティ、アントレプレナーシップなどをテーマとする実践的な学び
- 理系、工学系学部の新設、女性の進出
短期大学は、時代や受験生のニーズとアンマッチの傾向が時代が進むにつれて徐々に顕著になり、募集停止や廃止を行う大学が増えていった時代でもあります。
また、特に最近増えてきているのが、女子大学の共学化です。
私も入試系の部署経験がある1人の大学職員として、今の厳しい少子化の中、女子学生だけを受け入れる体制だけではやはり学生募集はつらい状況になると容易に予想できます。
大学業界全体にいえることですが、特に女子大学はこれまでの歴史同様に今後も大きな変化が求められていくことは間違いないです。
女子大学で働くってどんな感じ?
私自身は女子大学で勤務したことはないですが、以前に女子大学で働いていた経験がある同僚職員や他大学の女子大学職員の経験談をもとに紹介していきます。
また、私自身は複数の女子大学の中途採用選考を受けました。
女子大学は厳しい大学業界の中、特に改革や変革を求められる傾向が強いため、中途採用の募集も活発に行っている大学が多いです。(後ほど少し触れます。)
書類で落とされた大学もあれば、最終面接で落とされた大学もあり、選考中から見えてきた雰囲気や特徴もあわせて紹介していきたいと思います。
女性社会の傾向が強い
女子学生のみを受け入れる女子大学では、やはり職員(教員)も女性が多いです。
そのため、女性社会の雰囲気や風土に馴染み、仕事を行っていけないといけないため、逆にそこに馴染むことが難しければ長く働いていくことも難しいかもしれません。
一方で女性が多いことで、産休や育休、突然の子育て関連のお休みに関しては理解があるため、仕事とプライベートは両立しやすい雰囲気があります。
男性職員でも育休を取得している人は多いようです。
私は男性のため、本当の(?)女性社会を知っているわけではありませんし、もちろん男性職員もいるため女性社会へ飛び込んでいく必要はないと思いますが、女子大学で働くにあたっては把握しておくべきポイントだと思います。
学生との距離が近い
女子大学の特徴の1つとして、学生数が中~小規模の大学がほとんどということが挙げられます。
現在全国で女子大学の数は約70校ありますが、その中でも学生数が1番多い大学が、約9600人の武庫川女子大学です。
武庫川女子大学以下の大学は、学生数が7000人未満~1000人台の大学の規模となるため、中~小規模大学の特徴である学生との距離が近いことがほとんどの女子大学に当てはまる形となります。
その特徴を生かして、少数精鋭や面倒見の良さを売りにしている女子大学が多いため、職員の働きとしてもそこは期待されることになります。
特に学生対応がメインの部署では、淡白な対応ではなく、丁寧で真摯な対応がより女子大学においては求められることになります。
改革・変革志向を求められる
女子大学は女性のみを受け入れるため、厳しさが年々増している大学業界において、さらに受験生獲得が厳しい市場背景があります。
そのため、大学全体としては改革を求められる傾向があり、職員に対しても改革力・変化力が求められます。
改革の中で1番分かりやすいものが、やはり「共学化」でしょうか。
私がパッと想像しただけでも以下の大学が近年、共学化に舵を取り始めました。(詳しく調べると全国でより多くの大学が共学化を予定しています。)
女子大学の中で学生数がNo.1の武庫川女子大学の共学化が発表された際は、驚きました。
また、共学化という判断をせずに「募集停止」の判断をしている大学も増えてきました。
共学化となると、これまで行ってきた業務が部署によっては一新される可能性があります。
共学化だけでなく、多くの様々な変化に柔軟に対応する場面が特に女子大学で働くにあたっては、多く出くわすことになると思います。
女子大学の職員に向いている人は?

続いて、女子大学の職員として向いている人について、紹介していきます。
丁寧な対応ができる人
学生・職員・教員いずれの場面でも、女性とコミュニケーションをとることが多い女子大学の職員においては、共学の大学でももちろん求められますがより丁寧な対応や仕事ぶりが必要になります。
大学職員に求められる力の1つとして丁寧な仕事ぶりはありますが、例えば女性が上司になる可能性も高い女子大学で評価されるポイントとして特に見られることになると考えます。
また、学生や教員との対応の場面でも、円滑なコミュニケーションを図るためには、丁寧な対応は必須になるため、勢いだけの対応や適当な対応をしてしまう方は女子大学の職員としては、少し苦労する場面もあるかもしれません。
女性に理解がある人
女性と男性では、考え方や身体的な構造の違いがどうしても発生してしまうため、特に男性の方は頭に入れておく必要があります。
それは特に自身が上司や役職者となって、多くの女性職員をまとめる立場になった際に意識する必要があると考えます。
女性の思考や女性社会への理解がないと、いざそのような場面になった際に、上手くいかない場面もあるかもしれません。

私は企業時代に、そのような場面に出くわした際に、女性への指示やまとめる際に苦労した経験があります。
逆にそこを理解し、行動できる方は大いに活躍できるのではと思い、向いている人の特徴に挙げました。
女子大学の職員を選ぶ際のポイント
最後に、これまでのポイントもまとめつつ、女子大学の職員を選ぶ際のポイントを紹介します。
大学改革を積極的に行っているか
前述したように、女子大学は今後ますます厳しい時代を、生き抜いていかなければならない組織です。
それを達成するためには、やはり前年ベースの働きでは取り残されてしまうため、大学として積極的に改革を行っていかなければなりません。
女子大学の応募を迷う際は、学生数の規模や収支状況を見るのももちろんですが、直近に大学として改革や新たな取り組みを行っているかどうか・計画しているかどうかを指標にすることをおすすめします。
改革を積極的に行っている大学は、危機感を持って生き残っていこうとする意志があるため、すぐに大学が潰れるということは少なからずないと思います。
学生募集状況
学生募集状況は選ぶときに必ずチェックしてもらいたいポイントです。
現実として、多くの女子大学が学生募集に苦しんでいるということがあります。
定員の調整でどこか1年間だけ定員が充足してないというのは全く問題ないですが、3年連続で定員が充足していないなどの状況の大学は、少し危機感を覚えます。
もちろんなにか特段の事情がある大学もあるかもしれませんし、それだけがすべてではないので、参考までにしていただければ幸いです。
女性職員の比率
こちらは、男性向けのポイントになりますが、大学によっては在籍職員の性別の比率を公開している大学もありますので、もし公開していればチェックしてもらいたいです。
比率が半々の大学もあれば、女性職員の比率が8割の大学もあります。
同じような条件の大学であれば、合格のしやすさは比率が半々のほうが高くなるので、応募の際や入職後のイメージの際にポイントにすることをおすすめします。
女子大学は生き残れるのか
女子大学の職員として働く際のポイントやメリット、注意すべきこと、把握しておくべきことなどを紹介してきましたが、すべて読んでいただいた方は女子大学に対して多少マイナスなイメージを持ったかもしれません。
ですが、女子大学に限らず、今後の厳しい状況を生き抜いていくためには、どの大学においても同じことが言えます。
逆に、女子大学は共学の大学にはない「女性のみの大学」という最大の特徴であり売りがあります。
そこを存分にうまく広報等でアピールしていくことができれば、女子大学がなくなることはないと個人的に考えます。
また、女子大学に入りたい、女子大学に子供を入学させたいという層は、年々少しずつ少なくなっている傾向はありますが、いなくなるということは想像できません。

職員として働くにあたっても、その人の働き方や価値観にとって、ベストな環境になる方は多くいらっしゃると思います。
本記事で紹介したポイントを皆さんの価値観などと照らし合わせながら、満足のいく大学の選び方や採用選考の対策ができることを願っています!